『山月記』は、1942年に発表された中島敦の短編小説です。大清帝国(1644年〜1912年)の時代に集められた説話集『唐人説薈(とうじんせつわい)』を下敷きとして書かれており、詩人を目指しながら、自尊心を捨てることができずに才能を浪費し、虎の姿になってしまった男の胸中が語られる作品です。
横浜高等女学校で教員として働いていた中島敦は、国語と英語の授業を行う傍らで、この小説を書き上げました。持病の喘息の悪化により、天地療養のため役人としてパラオへ赴任することになると、彼はそれまでに書きためていた原稿を友人の作家に託しました。その原稿を読んで感動した友人は、雑誌『文學界』にこれらの作品を推薦し、その中でこの『山月記』を含む二篇の作品が掲載されることとなりました(中島敦は自分の作品が世に出たことを帰国後になって知りました)。現在では、高校国語の教科書にも頻繁に取り上げられ、その格調高い文章は、多くの人を魅了し続けています。このページでは、そんな『山月記』の登場人物、あらすじ、感想を紹介します。
※ネタバレ内容を含みます。
『山月記』の登場人物
李徴(りちょう)
隴西(ろうさい、中国西部、甘粛省にある地名。)の生まれ。若くして科挙の試験に合格して役人になるも、低い身分に甘じることができず、役人の座を辞して詩作にふけるようになる。生活が困窮して再び役人になるも、かつての同輩が出世していることに自尊心を傷つけられて発狂し、山の中に駆け出したまま行方がわからなくなっている。
袁傪(えんさん)
陳郡(ちんぐん、中国の中部、河南省にある地名)の生まれ。監察御吏(かんさつぎょし、地方の役人の監視、取締まりを行う役人)。李徴の同年の進士(科挙の試験に受かった者)で、最も親しい友人であった。
『山月記』のあらすじ
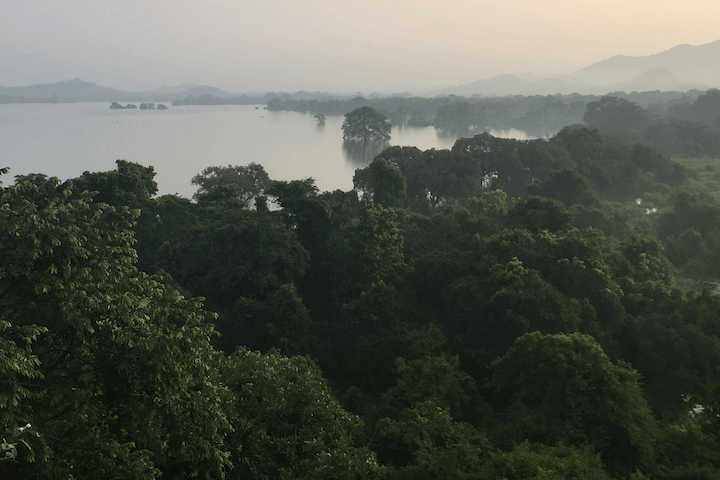
若い頃から優秀で、科挙の試験に合格して地方の役人になった李徴は、他人と相容れない性格で、身分の低い地位に甘んじることができず、役人を辞めて詩作にふけりました。しかし、詩人としての名をあげることができず、貧窮に耐えられなくなり、再び地方の役人の職に甘んじるようになりました。
かつての同僚が出世しているのを見た李徴は、自尊心を傷つけられ、公用で旅に出たときに発狂して山に入り、そのまま二度と戻ってきませんでした。
翌年、官吏の取り締まりの役人の袁傪という者が、ある河南省の宿に泊まり、朝早く出発しようとしていると、ここより先には人喰い虎が出るので、もう少し待ってから出発した方が良いと言われました。
袁傪は、旅の連れで混み合うのを危惧し、忠告を聞かずに出発しました。すると草むらの中から、一頭の虎が躍り出てきました。虎は、袁傪を襲うかに見えましたが、直ぐに引き返して草むらに隠れました。その方向から、「危なかった」という声を聞いた袁傪は、その声の主が、同年の科挙の試験を通過した親友の李徴であると気づきました。袁傪は温和な性格であったため、他人を寄せ付けない李徴の性格と衝突することがありませんでした。
袁傪が草むらに向かって話しかけると、忍び泣きのような声が聞こえ、その後で、自分は李徴であると返事をしました。
李徴は、自分の今の姿を晒すことはできないが、ほんの少しの間、懐かしい友人と話をしてくれないかと頼みました。
袁傪は不思議とその話を怪しむことなく受け入れました。彼は自分の近況を語った後、なぜ李徴が今のような姿になったのかを聞きました。
一年前、李徴が旅に出た時、ふと目を覚ますと、誰かが自分の名を呼ぶ声が聞こえ、思わずその声の方へ走り出しました。力が満ちるような気持ちで走っているうちに、彼は前足で地面を掴んでおり、気がつくと虎になっていました。そして目の前を兎が駆け抜けるのを見た途端に、人間であったことを忘れ、気がつくとその兎を仕留めていました。一日のうちに数時間は、人間の心が戻ってくるようでしたが、その時間は日を追うごとに少なくなっており、もう少しで自分は人間であったことを完全に忘れてしまうだろうと、李徴は語りました。
李徴は、人間であった記憶のあるうちに、まだ暗記しているいくつかの自分の詩を書き留めておいてほしいと袁傪に頼みました。袁傪は、部下に命じて、草むらの影から読み上げられる三十篇あまりの詩を書き取らせました。
それらの詩はすべて素晴らしいものばかりでしたが、一流のものになるには何か足りないところがあるように袁傪は感じました。
自分の不幸に同情する人々に向けて、李徴は話を続けました。彼は、人間であったころ、「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」のために、他人との交わりを避けていました。自分に才能があることを自覚していたものの、師についたり、仲間と切磋琢磨することで、才能の不十分なところが露呈するのを恐れ、努力を厭う怠惰な心に支配されてしまったのです。この「尊大な羞恥心」という猛獣を、心の中で飼い太らせたせいで、その内面にある猛獣が外面に現れたのではないかと、彼は語りました。そのような心の中の猛獣に抗いきれなかったことを後悔しても、山の頂の岩の上で吠えることしか、今の彼にはできませんでした。
虎に戻らなければならない時が来ると、自分が死んだと妻子に告げてほしいことと、彼らの生活が困窮することのないように取り計らってほしいということ、帰途は虎になった自分が襲いかかりかねないので、違う道を通ってほしいということを李徴は頼みました。
袁傪は別れの言葉を述べて馬に乗り、涙を流しながら出発しました。草むらからは、李徴の慟哭の声が聞こえました。
一行は丘の上に着き、李徴に言われた通り、来た道を振り返ってみました。すると一匹の虎が道に躍り出て吠え、そのまま元の草むらに戻っていったのが見えました。
管理人の感想
『山月記』は、虎になった李徴という男が、偶然通りがかったかつての友人の袁傪に、その胸中を語る物語です。李徴は、自分が虎になった原因を「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」のせいであると語ります。詩によって名をあげようと思いながらも、自分に才能がないのが判ることが恐ろしくて世間との交流を断ち、それでも自分を認めようとしない世間に憤り、世間に向けて心を開こうとしない自分を恥じ、そのような感情を飼い太らせた結果が、虎という猛獣となって現れたと言うのです。
虎にさせられたというと、なんだか凄く悪いことをしたかのように思われますが、李徴は誰にでも起こりうる悩みを増長させただけだという印象を受けます。たしかに人にはあまり好かれていなかったでしょうし、妻子を傷つけたりもしたようですが、彼がそこまで悪いことをしたようには思えません。
何かを夢見ながら、自分がその道で評価されるかわからずに、踏み出すことを躊躇してしまうのは、誰にでも起こりうることです。人はなにかと自分に言い訳をしながら、自尊心を傷つけられまいと逃げ回っているもので、恐れることを知らずに目標に向かって進み続けられる人の方がむしろ少ないのではないでしょうか。そのような意味で、李徴が袁傪に語ったことは、非常に共感しやすいものであると思います。だからこそ、李徴がもうすぐ人間の心を失わなければならないであろうことは、酷い不条理として感じられ、同情を誘います。
しかし、李徴は虎になったことで初めて、他人に自分の苦しみを語ることができたとも言えるでしょう。「ちょうど、人間だった頃、己の傷つき易い内心を誰も理解してくれなかったように。己の毛皮の濡れたのは、夜露のためばかりではない。」と彼が語ることからもわかるように、もし人間のままであったなら、袁傪は李徴にとって、たとえ親友と呼ぶことのできる存在であったとしても、その悲しい心の中をすべてさらけ出すことはなかったでしょう。
人間としての意識を失っていく土壇場の中で、袁傪を偶然見かけたことにより、藁をつかむような気持ちで、初めて李徴は自分の胸の内を明かし、自作の詩を後代に残すことができたのです。そして、虎となった李徴から逃げ出さずに、部下に詩を書き取らせ、妻子の面倒を見て欲しいという頼みを聞いてやった袁傪もまた、見事にその頼みに応えたと言えるでしょう。李徴は、初めて自分の苦しみを語ると共に、かけがえのない友情も手に入れたのではないでしょうか。次第に虎となっていく李徴の絶望に、ひとかけらの救いを袁傪が与えたのは間違いないと思います。
