桜の園(ロシア語:Вишнёвый сад)は、1903年に執筆され、1904年に出版されたロシアの劇作家アントン・チェーホフの最後の作品です。『かもめ』、『三人姉妹』、『ワーニャ叔父さん』とともにチェーホフの四大戯曲のうちのひとつに数え上げられる代表作の一つで、発表以来、多くの劇作家に影響を与え、世界中で上演されています。
1861年にロシア皇帝アレクサンドル二世によって宣言された農奴解放により、裕福な暮らしを得る元農奴が増える一方で、土地を経営する能力のない一部の貴族は貧困に陥るようになりました。この作品が発表されたのは農奴解放から四十年が経った後ですが、この影響がまだまだ色濃く残っていた時代で、没落貴族と呼ばれる人々がロシア各地に残っていました。
『桜の園』は、このような没落貴族の、抵当を支払うために競売に出されようとしている領地を舞台に、過去に取り残される人々と、未来に進んでいく人々の両方を描き、時代の転換点を表現した作品です。
初上演はロシアの演出家コンスタンティン・スタニスラフスキーにより、1904年の1月17日に、モスクワ芸術劇場で行われました。
発表当時、スタニスラフスキーはこの作品を悲劇として演出し、喜劇として書いていたチェーホフを怒らせたと言われています。しかしこのような意見の相違にも関わらず、この封切りは大成功を収め、多くの主要な地方都市ですぐに上演され、この成功はロシアだけにとどまらず、すぐに海外でも大きな評価を得ることとなりました。チェーホフは間もなく結核が悪化し、同じ年の七月に死去しますが、その後もこの作品は喜劇と悲劇の二面性を持つものとして、演出家の間で活発な議論が行われています。
日本においては、この作品にヒントを得た太宰治が、『斜陽』という作品を発表し、昭和初期のベストセラーのうちの一つとなっています。
このページでは、『桜の園』の登場人物、あらすじ、感想を紹介します。ネタバレ内容を含みます。
『桜の園』の登場人物
リュボーフ・アンドレーエヴナ・ラネーフスカヤ
愛称リューバ。桜の園の女地主。六年前に夫を亡くし、その翌年に七歳であった息子のグリーシャが川で溺死したため、新しい恋人とともに外国で過ごしていた。その恋人に逃げられ、五年ぶりに桜の園に戻ってくる。家計が傾いていることを知りながら、昔の習慣を捨てられず、散財を繰り返している。
アーニャ
ラネーフスカヤ夫人の娘。十七歳。シャルロッタとともにラネーフスカヤ夫人をパリに迎えに行き、ロシアに連れ戻す。一家の置かれた状況をしっかりと理解しており、トロフィーモフの革新的な考えに同調し、働くことを決意する。
ワーリャ
平民出のラネーフスカヤ夫人の養女。二十四歳。外国へ旅立ったラネーフスカヤ夫人の代わりに桜の園を切り盛りしていた。かねてからロパーヒンとの結婚が噂されているが、将来は僧院にこもることを考えている。
レオニード・アンドレーエヴィチ・ガーエフ
愛称リョーニャ。ラネーフスカヤの兄。五十一歳。妹と同じように貴族としての習慣を捨てられず、桜の園を別荘地にするというロパーヒンの案に憤慨する。
ボリース・ボリーソヴィチ・シメオーノフ(ピーシチク)
不景気に見舞われている地主。返済に追われ、ラネーフスカヤ夫人に繰り返し借金を申し込む。
ピョートル・セルゲーエヴイチ・トロフィーモフ
愛称ペーチャ。大学生。七歳で川で溺れて死んだラネーフスカヤ夫人の息子グリーシャの家庭教師をしていた。
シャルロッタ・イワーノヴナ
アーニャの家庭教師。見せ物をしていた両親に連れられて各地を渡り歩いてきたため、自分の正式な出生を知らない。アーニャと共にラネーフスカヤ夫人をパリに迎えに行き、ロシアに連れ戻す。
エルモライ・アレクセーエヴィチ・ロパーヒン
裕福な商人。父親がラネーフスカヤ夫人の父親の農奴であったため、昔の主人を今でも慕っている。競売に出されることになっている桜の園を別荘地として貸し出す提案を行う。
セミョーン・パンテレーエヴィチ・エピホードフ
桜の園の執事。不器用で運の悪い男。ドゥニャーシャに想いを寄せている。
ドゥニャーシャ
桜の園の家政婦。エピホードフに結婚を申し込まれたものの、パリから戻ったヤーシャに惹かれる。
フィールス
耳の遠い八十七歳の老僕。先代の裕福だった頃の暮らしを懐かしんでいる。
ヤーシャ
ラネーフスカヤ夫人のパリ滞在に付き添っていた若い従僕。夫人とともにロシアへと戻り、ドゥニャーシャを誘惑する。
『桜の園』のあらすじ
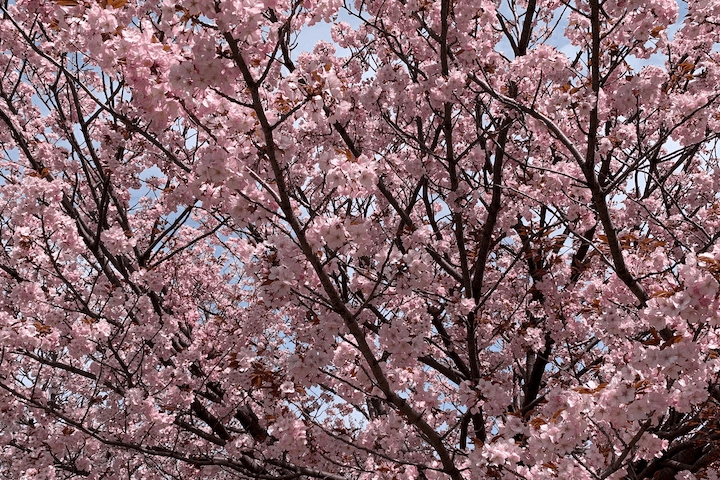
第一幕
五月のある寒い早朝、「桜の園」と呼ばれる貴族の土地であった邸宅に、その領地の女主人であるラネーフスカヤ夫人が五年ぶりに戻ってきます。
ラネーフスカヤ夫人は、六年前に夫を亡くし、五年前に息子のグリーシャが川で溺れ死んで以来、フランスで病気の恋人を看病しながら暮らしていました。しかしその恋人に金を巻き上げられた挙句に逃げられてしまい、毒を飲もうとしたところで急に帰りたくなってロシアに手紙を書きました。その連絡を受けた夫人の十七歳になる一人娘のアーニャと、その家庭教師シャルロッタは、パリへ渡り、同行者の下男ヤーシャと共にラネーフスカヤ夫人を連れ帰ったのでした。
桜の園の住人と、出入りしていた人々は一行を出迎え、ラネーフスカヤ夫人との再会を果たしました。
屋敷の女中ドゥニャーシャは、執事のエピホードフから結婚を申し込まれていましたが、彼がそそっかしく、不運で、訳の分からないことを話すので、承諾するかどうかを迷っていました。彼女は五年ぶりに戻ったヤーシャを見て、見違えるようになったと思いました。ヤーシャは、ドゥニャーシャに気づくと、彼女のことを抱きしめました。
父親がこの領地の農奴で、今では裕福な商人になっているロパーヒンは、敬愛するラネーフスカヤ夫人と、その兄のガーエフに、このままでは桜の園が近く競売に出されることを語り、その一部を別荘地にして収入を得、土地を維持する提案を行いました。しかし、そのためには、この高名な桜の木々を伐採し、屋敷も壊さなければなりませんでした。
ここを出入りしていて、借金に首が回らなくなっている地主ピーシチクは、担保の利子を払わなければいけないので二百四十ルーブルを貸して欲しいとラネーフスカヤ夫人に頼みました。ラネーフスカヤ夫人は、仕方なくガーエフに頼んでその金を出してやりました。
この屋敷には、一昨日からグリーシャの家庭教師であった大学生トロフィーモフがやって来ていました。トロフィーモフは五年前と比べてすっかりと老け込み、ラネーフスカヤ夫人はその変貌ぶりに驚くと同時に、グリーシャのことを思い出させられ、涙を流しました。
夜になり、ラネーフスカヤ夫人が引き取ると、アーニャ、ガーエフ、そしてラネーフスカヤ夫人の養女でこの土地を任されていたワーリャは、桜の園を競売から守る方法を話し合い、それぞれ希望を抱きながら眠りにつきました。そこへ通りがかったトロフィーモフはベッドに運ばれるアーニャを見て、「僕の太陽!僕の青春!」と呟きました。
第二幕
桜の園近くの見捨てられた礼拝堂で、エピホードフはギターを演奏し、ヤーシャと声を合わせて歌います。彼らはそばにいるドゥニャーシャをお互いに意識しています。
アーニャの家庭教師シャルロッタは、旅芸人の子として育ち、ドイツ人の奥さんに拾われて教育を受け、家庭教師になった経緯を語ります。
ヤーシャに夢中になっていたドゥニャーシャは、エピホードフの求婚の返答をはぐらかします。そしてヤーシャと二人きりになると、愛情を確かめようと、彼をいきなり抱擁します。外国に行くことを考えているヤーシャは、そんなドゥニャーシャをろくに相手にせず、誰かが来る音がすると、彼女を遠くへと行かせます。
そこへラネーフスカヤ夫人、ガーエフ、ロパーヒンがやって来ます。
ロパーヒンは、この土地を別荘地として出すのに賛成かどうかの判断を二人に迫りました。しかしラネーフスカヤ夫人とガーエフは、別荘客の俗悪なことを嫌い、借金を返すためにヤロスラヴリの大伯母から融資してもらうという不確かな方法について語り合いました。
ラネーフスカヤ夫人は、働き詰めのロパーヒンの暮らしを不趣味だと言い、かねてから屋敷中で噂されていたワーリャとの結婚を勧めました。
八十七歳になる耳の遠い老僕のフィールスは、自分達が若かった頃の古き良き時代についてガーエフと語り合いました。
トロフィーモフも、アーニャとワーリャを連れて現れました。
やがて日が沈むと、浮浪人がやってきて、施しを乞いました。ワーリャが怯えたため、ラネーフスカヤ夫人はその浮浪人に金貨を渡しながらも、また金を使ってしまったことを後悔し始めました。
やがて皆が夕食に去って行き、トロフィーモフとアーニャだけが残されました。二人は自分たちが恋愛を超越したものによってお互いに結び付けられていると信じるようになっていました。トロフィーモフは、ロシア人はこれまでの堕落した奴隷制度と決別し、皆が不断の勤労を行わなければならないのだという持論を述べました。アーニャはトロフィーモフの考えに深く同調し、自分達の手を離れてしまうこの屋敷から出て行き、新しい人生を始めることを決意しました。
第三幕
桜の園の客間では、舞踏会が開かれており、シャルロッタは、手品や腹話術を披露しています。
ガーエフとロパーヒンは、競売に出かけており、その帰りが遅いことをラネーフスカヤ夫人は心配しています。
ワーリャは、ヤロスラヴリの金持ちの大伯母が委任状をよこし、自分の名義で買い戻すようにと言ってきたので、ガーエフが落札するのは間違いないだろうとラネーフスカヤ夫人を慰めました。ラネーフスカヤ夫人は、領地のことで気を揉みながらも、毎日電報を送ってくるパリの恋人のところへ戻ることを真剣に考えるようになっています。そんな彼女に対して、トロフィーモフは真実をまともに見るようにと警告して言い争いになり、部屋から出て行った挙句に階段から落ちてしまいます。ラネーフスカヤ夫人は、彼のことを笑って許し、二人はすぐに和解しました。
フィールスは、将軍や貴族が踊りにきていた以前の舞踏会に比べ、今では駅長、郵便の役人などを招くだけとなってしまったことを嘆きました。ヤーシャは、パリへ行くことがあったら、自分にお供させて欲しいとラネーフスカヤ夫人に頼みました。
エピホードフは、自分には興味がなくなったらしいドゥニャーシャに話しかけ、不幸には慣れていると自嘲しました。ワーリャは仕事をせずにふらふらしている彼を叱り、二人は口論になりました。
そこへロパーヒンとガーエフが競売から戻りました。
ラネーフスカヤ夫人が結果を尋ねると、ロパーヒンは、自分が桜の園を買ったのだと答え、ここの木を切り倒して別荘地にすると宣言しました。
ラネーフスカヤ夫人は倒れそうになり、椅子に腰掛けて激しく泣きました。アーニャは、ここから出て新しい庭を作ろうと夫人を慰めました。
第四幕
数週間後、桜の園を引き払うための準備を終え、窓のカーテンも壁の画もなくなった部屋に、ラネーフスカヤ夫人とガーエフが入ってきます。ラネーフスカヤ夫人は、パリに行き、ヤロスラヴリの大伯母が送ってくれたお金で暮らすことを決めていました。ガーエフは、ハルキウで年に六千ルーブルという銀行の職に就くことになっていました。
ガーエフらと一緒にハルキウで一冬を過ごすことを決めていたロパーヒンと、大学に在学しながらモスクワに行くつもりのトロフィーモフは、人生に対して対立した意見を持ちながらも、友情を交歓して別れました。
遠くの方では、早くも桜の木に斧を打ち込む音が聞こえ、アーニャは、ラネーフスカヤ夫人が出かける前にそのような指示を出したロパーヒンを叱責しました。ロパーヒンとトロフィーモフは、木を切るのをやめさせに出て行きました。
病院に入る予定だったフィールスが紹介状を置いていなくなったため、アーニャは、追いかけて持たせてやらなければならないと、出て行きました。
ラネーフスカヤ夫人に同行することが決まっていたヤーシャは、ドゥニャーシャにはもはや興味がありませんでした。ドゥニャーシャは、彼に泣きながらすがりつき、パリから便りをよこしてほしいとせがみました。
アーニャは、女学校の検定試験を受け、働いて、いつか母の暮らしを助けるつもりでした。
ラネーフスカヤ夫人は、いつか帰ってくることを約束し、アーニャに別れを告げました。
シャルロッタはこの家から出て行くつもりで、勤め口を探して欲しいとロパーヒンに頼みました。
自分の土地から見つかった粘土をイギリス人に貸すことができたピーシチクは、これまでの借金をすべて返す目処を立てることができるようになっていました。
ラネーフスカヤ夫人は、桜の園の運営という仕事がなくなったワーリャを心配し、ロパーヒンに結婚を申し込むように急かしました。ロパーヒンは、ワーリャに結婚を申し込む決意をして話しかけましたが、人に呼ばれ、プロポーズをすることなく出て行きました。
ワーリャは静かに咽び泣きました。
出発の時になり、アーニャ、シャルロッタ、トロフィーモフ、ワーリャ、ロパーヒンが部屋を出ていくと、ラネーフスカヤ夫人とガーエフも涙を流しながら去って行きました。そこへ病院へ行っていたはずのフィールスが現れ、皆が行ってしまったことを悟ると、精魂尽き果てた様子で横になりました。
あとには木に斧を打ち込む音だけが残されました。
管理人の感想
『桜の園』は、ロシアを代表する劇作家チェーホフの代表作で、今なお古典として世界中で上演され続けている戯曲です。
日本においても、この作品に着想を得た太宰治が『斜陽』を書いてベストセラーになったこともあり、人気のある作品です。『ハムレット』や『ロミオとジュリエット』などのシェイクスピア劇と共に、文学に興味を持つ多くの人が戯曲の入門として読む作品のうちの一つに挙げられるでしょう。
しかし、それまで小説ばかり読んでいた人にとって、戯曲を理解するというのは非常に難しいもので、なかなか初見でこれを楽しむというところまでいく人は少ないんじゃないかと思います。
そもそも戯曲は、読者のために書かれるものではなく、観客のために書かれるものです。観客は、脚本に書かれている台詞だけでなく、俳優の動作、表情、服装、さらには舞台の背景や演出といった、視覚と聴覚によって得られる情報のすべてから作品を理解することができます。それは文字を読むよりもはるかに短時間で、一度に多く得られる情報です。たとえば舞台に豪奢な内装を施しておけば、そこに住む住民が裕福であることが自ずと理解できるように、そのような情報をいち早く得ることのできる観客にとっては、台詞による詳しい説明は不要であるばかりか、時に物語のテンポを妨げたり、「くどい」といった印象を抱かせる原因ともなり得るものです。また(特に近現代の)戯曲は、限られた時間内での上演に収める必要もあるので、優れた劇作家ほど、わざわざ俳優が喋らなくても良い所は、台詞に起こさないのではないかと思います。
また戯曲は、(ト書きにある程度の説明が書かれていることはありますが)小説のように、書き手による文章(台詞以外のところ)がないため、会話の中の自然な流れの中で、登場人物の置かれている状況を説明しなければなりません。たとえば、「ラネーフスカヤ夫人は没落貴族でありながら、そのことを自覚できずに散財する癖が治らないのだった」とは言わずに、「マントンの近くのご自分の別荘も売ってしまったし、ママにはもう、なんにも残っていないの、(中略)だのにママったら、ちっともわからないの。駅の食堂へはいると一ばん高い料理を注文するし、ボーイのチップは一ルーブリずつなのよ」となるわけです。もちろん小説においてもこのような表現は当たり前ではあります(むしろ、このような表現が多いほど優れた作品であるとも言えます)が、戯曲では、すべてをこれで賄わなければならず、その分台詞にすると不自然になってしまう直接的な説明が自ずと少なくなるのではないかと思います。このような傾向は、シェイクスピア劇に比べてもチェーホフ劇において特に顕著であり、登場人物に「そのまま説明させる」ことが少ないために、彼らの一つ一つの言葉が何を意味しているのかを考えなければならず、難解です。しかし、その分、自然な会話の流れの中に作品を把握するためのヒントがところどころに隠されており、繰り返し読むほどに、まるで宝探しをするような感覚で理解していくことができる作品だと思います。
その中では、『桜の園』は、農奴解放という大きなパラダイムシフトの中で、時代に取り残されていく人々と、新しい時代に適応していく人々の対比といった構図が鮮明で、チェーホフの作品の中では、比較的分かり易い作品であると思います。
作品の舞台は、農奴解放令によって没落した貴族の領地です。抵当を支払うために競売に出されるようになったこの土地に、五年間フランスで暮らしていたラネーフスカヤ夫人が戻ってきます。裕福だった頃の癖が抜けない夫人は、自分の土地がなくなるという実感が持てず、いまだに散財を繰り返しています。
父親がこの土地の農奴で、今は裕福な商人になっているロパーヒンは、若い頃からラネーフスカヤ夫人を慕っており、なんとか桜の園を維持しようと、ここを別荘地にして収入を得ようと提案します。しかし、ラネーフスカヤ夫人や、その兄のガーエフは、別荘客の下品なことを嫌い、その提案を相手にしません。
ラネーフスカヤ夫人、ガーエフ、そして老僕のフィールスは、時代の変化に適応できない人々です。彼らはやがて来る滅亡を予感しながらも、桜の園が競売に出されることを阻止するための財力もなく、古き良き時代の思い出に浸り、破滅をただ待っているだけのようにも見えます。
対して、ロパーヒン、アーニャ、トロフィーモフ、ヤーシャ、ドゥニャーシャらは、新しい時代に生きる人々です。彼らも桜の園を他人の手に譲らなければならないことをそれなりに憂いてはいるようですが、その現実をしっかりと見つめ、自分がその後どのように生きるべきかと考えながら、それぞれの人生を模索しています。
このような現状を理解しながらも将来は尼寺に入ろうとしているワーリャ、古い貴族でありながら幸運によって未来を掴むピシーチク、自分が進歩している人間だと思い込んで中途半端な知識をひけらかすエピホードフ、そして彼らとは一線を画しているようにも見えるシャルロッタといった人物たちにも、それぞれの立ち位置があり、これを初見で理解していくのはなかなか難しいですが、一人一人が舞台上でどのように演技されるのかを想像しながら繰り返し読むと、自ずと彼らの個性が浮かびあがり、共感を覚えやすいのではないかと思います。
いつの時代でも、過去にしがみついている人、未来を見据えようとしてもなかなかそれができない人もいれば、そのような人を心配してあれこれと手を尽くしてあげる人、あるいは馬鹿にしてかかる人が存在しているものです。19世紀ロシアの没落貴族の話と聞くと、遠い世界のように感じますが、深く読み込むほどに、我々と同じような人々が抜き差しならない状況に立たされたときに抱く感情が表現された作品なんだということが理解できるはずです。そしてそれぞれの登場人物に共感するほどに、読み終えた時にはなんとも言えない深い余韻を与えてくれる作品だと思います。
